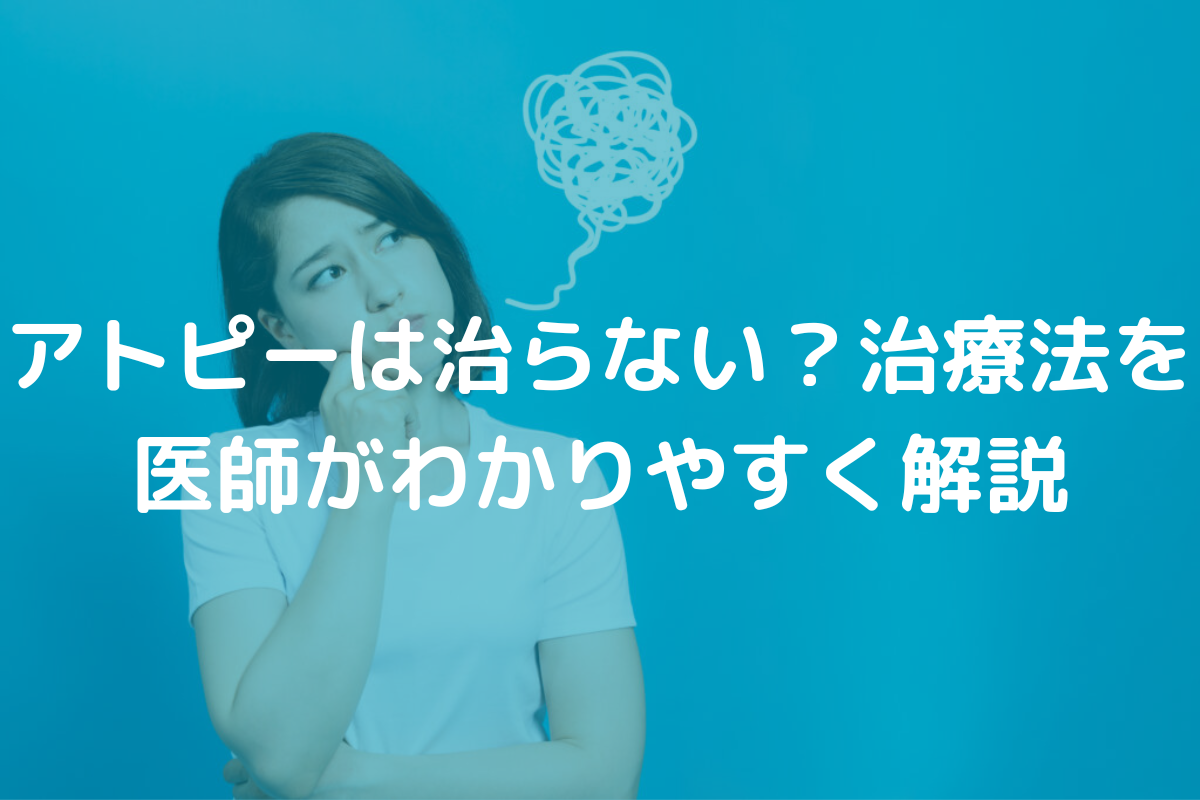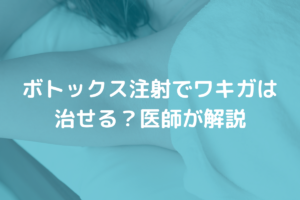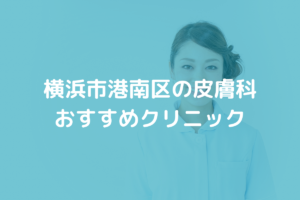アトピー性皮膚炎は、増悪と寛解を繰り返す痒みのある湿疹を主病変とする疾患です。今回は、アトピーが治りにくい理由や治療法について解説します。

江野澤 佳代 医師
東邦大学医学部卒業、東邦大学医療センター大森病院研修医、東邦大学医療センター大森病院皮膚科、東京高輪病院皮膚科、東京高輪病院皮膚科医長、2020年10月に浅草橋駅前総合クリニック開院
日本皮膚科学会、日本美容皮膚科学会、日本皮膚科学会認定皮膚科専門医
アトピーとは

アトピー性皮膚炎とは、増悪と軽快を繰り返す痒みのある湿疹を主病変とする疾患です。乳児期あるいは幼児期から発症し小児期に寛解する場合もありますが、寛解することなく悪化を繰り返し、成人まで持続することも多いとされています。
患者さんの多くは気管支喘息、アレルギー性鼻炎や結膜炎、アトピー性皮膚炎のいずれかの家族歴や既往歴、またはIgE抗体を産生しやすいといった「アトピー素因」を持ちます。
左右対称性に皮疹が生じますが、年齢によって好発部位が異なります。乳児早期は、頭部や顔面などの露出部に初発し、頸部、さらには腋窩、肘窩、膝窩などの間擦部に拡大し、体幹や四肢全体にも及びます。幼児期から学童期にかけては、顔面の皮疹は減少する一方、頸部、腋窩、肘窩、膝窩、鼠径、手足関節の皮疹が著明となります。
思春期以降は、顔面、頸部、体幹などの上半身の皮疹が悪化する傾向があります。乳児期の皮疹のコントロールが不良である場合は、経皮的感作による食物アレルギーや喘息の発症(アレルギーマーチ)のリスクが高まると考えられています。
アトピーの診断と検査

診断においては、皮膚症状の経過と性状を正確に評価することが基本となり、血清IgE値などの血液検査は補助的なものになります。
アトピー性皮膚炎は、上記のように慢性に経過する、左右対称性で、年齢ごとに特徴のある分布を示す皮疹から診断します。
皮疹の経過や性状が類似したさまざまな疾患(菌状息肉症やSezary症候群などの皮膚T細胞リンパ腫、疥癬、皮膚筋炎など多数)の鑑別が重要で、必要性に応じて病理学的検査などを行うこともあります。
重症度の判定は、治療方針を決める際に欠かせない、他覚的評価として、血清TARC値などを適宜施行します。また、増悪因子の検索目的で、パッチテストや抗原特異的IgE検査などを行うこともあります。
アトピーの治療法

まず、「症状がないか、あっても軽微で、日常生活に支障がなく、薬物療法もあまり必要としない状態に到達し、それを維持する。また、このレベルに到達しない場合でも症状が軽微ないし軽度で、日常生活に支障をきたすような急な悪化が起こらない状態を維持すること」(アトピー性皮膚炎診療ガイドライン2021)という治療の目標を医師と患者さんが共有することが大切です。
軽症の場合は、外用治療(ステロイド、タクロリムス、デルゴシチニブ、ジファミラスト、各種保湿剤など)を適切に行います。
中等症・重症の場合は、プロアクティブ療法を含む外用治療の強化に加えて、光線療法、さらには様々な全身療法の併用を要します。
全身療法に使用する治療薬には、従来からのシクロスポリンに加えて、生物学的製剤(デュピルマブ、ネモリズマブ、トラロキヌマブ、レブリキズマブ)、低分子化合物(JAK阻害薬;バリシチニブ、ウパダシチニブ、アブロシチニブ)の使用が可能になり、目標達成をより明確に見通せるようになりました。
まとめ
アトピー性皮膚炎の病態は、「タイプ2炎症を主体とした免疫学的異常」、「皮膚バリア機能低下」、「痒み」の3つの側面が互いに関係し悪循環をきたすことにより形成されています。
角質バリアの障害は、炎症や痒みの惹起、タイプ2型の免疫誘導の要因となり得ます。
発汗機能の回復は皮膚バリア機能の回復につながりますが、過度の汗の長期間の付着は皮膚バリア機能の障害や痒みの惹起につながるので、大量発汗時は清拭やシャワーなどで汗を除去するようにしましょう。
また、精神的ストレスや身体的ストレスは皮膚炎や痒みの悪化原因となるため、規則正しい生活をこころがけましょう。
参考文献